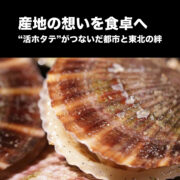火山灰が育てる、干物の芸術 ― 「灰干し」の伝統と、唯一無二のうま味に迫る ―

取材・文:小室

■ 「これ、どうやって干してるか分かりますか?」
鹿児島の港町に立ち寄ったとき、干物の美しさに思わず足を止めた。
表面はつややかで、肉厚で、見るからに旨味が閉じ込められているのが分かる。
「これ、“灰干し”って言うんですよ」
と、静かに語り出してくれたのは、柳川さん。
小室:「灰干し……火山灰を使うって、本当なんですか?」
柳川さん:「はい。桜島の火山灰100%を使って、魚の身をセロファンと不織布で包み、上下から灰で挟む。これが灰干しの製法です」
■ セロファンと火山灰で、「旨味を凝縮する」
小室:「どうして火山灰を使うと、そんなにおいしくなるんですか?」
柳川さん:「理由は3つあります。
1つは火山灰が“多孔質”で、臭みと水分を吸収してくれること。
2つめはセロファンの浸透圧で、旨味成分(アミノ酸)が魚に残ること。
そして3つ目は酸化しにくい環境で熟成できること。
つまり、“脂が酸化せず、旨味だけが凝縮された魚”ができるんです」

■ 受け継がれる知恵。「文化干し」からの進化
小室:「この製法って、最近生まれたものなんですか?」
柳川さん:「いえ、ルーツは1950年代にあります。
当時はセロファンを使った干物が“文化的”と評され、“文化干し”という言葉が生まれました。
そして1960年代に“灰干し”という独自製法として確立。以来、途絶えることなく作り続けられてきました」
小室:「セロファンと火山灰、まさに“昭和の知恵と自然の恵み”の融合ですね」

■ 灰干しの手仕事。そのすべてが“手間の価値”
柳川さん:「流水で洗って、食塩水に浸けて、1枚ずつセロファンと不織布で包み、火山灰で挟んで、冷蔵庫で24時間以上熟成。
……正直、手間しかありません(笑)」
小室:「それでもやり続けている理由は?」
柳川さん:「“この味じゃないとダメ”と言ってくださる方がいるからです。
それと、家庭のグリルで焼くだけでプロの味になるって言っていただける。
それが灰干しの魅力だと思っています」
■ 編集後記:「焼くだけで、ごちそうになる」
手間も時間も、いまの時代では“効率的ではない”。
でも、その非効率こそが、唯一無二の味を生んでいた。
焼きたての灰干しを一口食べて、私は驚いた。
皮はパリッと香ばしく、身はふっくら。そして何より臭みが全くない。
これは、“干物の再定義”かもしれない。
次に魚を焼くとき、あなたもきっと灰干しを思い出すだろう。